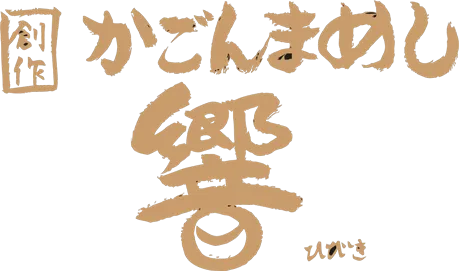居酒屋で失敗しない正月飾りの選び方とマナー徹底解説
2025/11/26
新年を迎える準備として、居酒屋で正月飾りに悩んだ経験はありませんか?居酒屋は多くの人が集う場所だからこそ、装飾一つ取っても伝統やマナーに気を配りたいところです。しかし、飾る場所やタイミング、種類やマナー、さらに地域による違いまで考えると、何をどう選んで飾るべきか意外と迷ってしまうもの。本記事では、居酒屋ならではの正月飾りの選び方や飾り付けの正しいマナー、避けるべきタブーや失敗しないポイントを徹底解説します。この記事を読むことで、安心して新年を迎えられる店舗演出が実現でき、来店されるお客様にも心地よい年始の雰囲気を届けられるでしょう。
目次
居酒屋で新年を彩る正月飾りの基本知識

居酒屋で選ばれる正月飾りの種類と特徴
居酒屋でよく選ばれる正月飾りには、門松、しめ飾り、鏡餅などの伝統的なものが中心です。これらは新年を祝い、店内に縁起をもたらす意味が込められています。特に門松は玄関先に置くことで年神様を迎え入れる象徴となり、しめ飾りは悪いものの侵入を防ぐとされています。
店内の装飾としては、松竹梅や南天、水引、紅白のアイテムを取り入れることで華やかさとお祝いムードを演出できます。最近ではコンパクトなサイズの正月飾りや、カウンターやテーブルに置けるアレンジも人気です。
選ぶ際は、店舗の広さや雰囲気、来店客層に合わせて装飾の大きさやデザインを調整することが大切です。過度な装飾は動線を妨げる場合があるため、実用性も考慮して選びましょう。

新年にふさわしい居酒屋正月飾りの意味
正月飾りにはそれぞれ意味があり、居酒屋においても新年のご利益やお客様の健康・商売繁盛を願う気持ちが込められています。門松は年神様を迎えるための目印、しめ飾りは清めと厄除け、鏡餅は円満や長寿の象徴です。
居酒屋では、こうした意味を理解したうえで飾ることで、来店されたお客様にも日本のお正月文化や店舗の心意気を伝えられます。例えば、松竹梅の飾りは「繁栄」「健康」「長寿」を表し、南天は「難を転ずる」縁起物として人気です。
飾りの意味をスタッフで共有したり、簡単な説明をPOPに記載することで、会話のきっかけや店舗イメージの向上にもつながります。意味を知ることで、より丁寧な新年の演出ができるでしょう。

居酒屋で人気の正月飾りレイアウト術
居酒屋の正月飾りレイアウトは、入口・カウンター・個室・トイレ前など、動線と視認性を意識して配置するのがポイントです。入口には門松やしめ飾り、カウンターやテーブルには小型の鏡餅や水引飾りが映えます。
店舗らしい演出を目指すなら、照明や器、既存の内装とのバランスを考えて飾りを選びます。例えば、和モダンな雰囲気ならシンプルな水引やモノトーンの松飾り、賑やかな大衆居酒屋なら色鮮やかな紅白や南天を取り入れると統一感が出ます。
レイアウト時の注意点としては、通行や配膳の妨げにならない場所を選ぶこと、火気の近くには飾らないことです。実際にスタッフや常連客の動線を確認しながら最適な配置を心がけましょう。

店舗らしさを引き立てる飾りの選び方
居酒屋の個性を活かすためには、店舗のイメージや客層に合わせた正月飾りを選ぶことが重要です。例えば、落ち着いた和食居酒屋なら伝統的な門松やしめ飾り、若者向けのカジュアルな店ならポップな色使いや現代的なデザインの飾りが適しています。
具体的には、地元の特産品や地域色を取り入れた飾りを選ぶことで、他店との差別化や話題づくりにもなります。お客様の声を参考に、毎年少しずつ飾りを変えるのもリピーター獲得のポイントです。
選び方の注意点としては、過剰な装飾はかえって店舗の雰囲気を壊す場合があるため、全体のバランスを見ながら選定しましょう。装飾品の購入や手作りの際は、耐久性や衛生面にも十分配慮が必要です。
正月飾りを選ぶなら居酒屋らしさも大切に

居酒屋に合うお正月飾りの選び方ポイント
居酒屋で正月飾りを選ぶ際は、店舗の雰囲気や客層に合わせて装飾を工夫することが大切です。まず、伝統的な門松やしめ飾り、鏡餅などの正月飾りは、新年の神様を迎える意味があり、多くの店舗で取り入れられています。しかし、居酒屋の場合は設置スペースや安全面、混雑時の動線も考慮しなければなりません。
また、正月飾りの種類によっては縁起物としての意味が異なるため、場所や用途に応じて選ぶのがポイントです。例えば、カウンターや各テーブルには小ぶりのしめ飾りやミニ門松を、入口には存在感のある門松を設置するなど、店舗全体のバランスを意識しましょう。お客様が年始の雰囲気を感じやすいよう、装飾の配置や色合いにも配慮することが求められます。
失敗例として、通路に大きな飾りを置きすぎてお客様の移動を妨げてしまうケースや、店内の雰囲気と合わない華美すぎる装飾が逆効果になることもあります。正月飾りを選ぶ際は、実際の設置場所やお客様の動線を確認し、過度にならないよう注意しましょう。

店舗らしさを表現する正月飾りの工夫
居酒屋ならではの正月飾りを取り入れることで、他店との差別化や店舗の個性を表現できます。例えば、地域の伝統や地元の縁起物を飾りに取り入れることで、地元愛や親しみやすさをアピールできるでしょう。特に、鹿児島の居酒屋であれば、南天や松竹梅など、地域に根付いた素材を使った飾り付けが効果的です。
また、店舗のコンセプトや内装デザインに合わせて、飾りの色使いや素材選びを工夫することも大切です。和モダンなインテリアには水引を使ったシンプルな装飾、古民家風の店舗には素朴な手作り感のあるしめ縄など、店舗の雰囲気にマッチした飾り付けを心がけましょう。
お客様から「毎年違った飾りが楽しみ」といった声をいただくこともあり、リピーター獲得にも繋がります。店舗らしさをどう表現するか迷った場合は、スタッフでアイデアを出し合い、試作品を作ってみるのもおすすめです。

居酒屋で映えるモダンな正月飾りアイデア
近年は伝統的な正月飾りに加え、現代的なアレンジを取り入れたモダンな飾りも注目されています。居酒屋のインテリアに合うよう、和紙や水引を使ったシンプルなリース型しめ飾りや、紅白のオーナメントを使った装飾などが人気です。これらは手軽に設置でき、店内の雰囲気も一新できます。
さらに、LEDライトを活用した演出や、テーブルごとに小さな鏡餅や松のミニアレンジを配置することで、写真映えする空間を作ることも可能です。特に若い世代のお客様には、SNS映えする装飾が好評で、来店のきっかけになることもあります。
注意点としては、照明や火気の近くに装飾を設置しないことや、素材が落下しないようしっかり固定することが大切です。安全面に配慮しつつ、現代的なセンスを加えることで、幅広い世代のお客様に楽しんでもらえるお正月演出が実現できます。

お正月飾りpopで店内の雰囲気を演出
お正月飾りに加えて、店内の雰囲気を盛り上げるためにおすすめなのがPOPの活用です。正月限定メニューやお祝いのメッセージをPOPで掲示することで、季節感を手軽に演出できます。特に、手書きの温かみあるPOPや和紙を使ったデザインは、居酒屋の和の雰囲気と相性が良いです。
また、POPのレイアウトや配置場所にも工夫が必要です。入口やカウンター、各テーブルなど、お客様の目に留まりやすい場所に設置することで、自然と正月ムードを感じてもらえます。POPには鏡餅や門松などのイラストを添えると、より一層季節感がアップします。
失敗例として、情報量の多すぎるPOPや派手すぎる色使いは逆効果になる場合があるため、内容を絞り、読みやすさを重視しましょう。お客様からの反応を見ながら、毎年少しずつデザインを変えることで、リピーターにも新鮮さを提供できます。

和の心を伝える居酒屋正月飾りの提案
正月飾りには日本の伝統や和の心を伝える大切な役割があります。居酒屋で飾る場合、お客様が店内に入った瞬間から新年の特別感を感じられるよう、玄関やカウンター、トイレなどにもさりげなく飾りを配置するのがポイントです。特に、玄関や入口には門松やしめ飾りを飾ることで、年神様を迎える意味をしっかり伝えられます。
また、鏡餅や南天などの縁起物は、店内の目立つ場所に設置し、和のお祝いムードを演出しましょう。飾りを通じて「おもてなし」の心を伝えることで、初めて来店される方にも温かい印象を与えられます。スタッフが飾りの意味をお客様に説明できるようにしておくと、会話のきっかけにもなります。
注意点としては、正月飾りには飾ってはいけない日やタブーもあるため、地域や伝統に配慮した運用が必要です。例えば、12月29日や31日は「苦」や「一夜飾り」とされるため避けるなど、基本的なマナーを守りながら、和の心を伝えることを心掛けましょう。
伝統を大切にした居酒屋の正月飾り演出

居酒屋で伝統を守る正月飾りの飾り方
居酒屋で正月飾りを飾る際には、伝統を尊重しつつ店舗の雰囲気やお客様の動線を考慮することが重要です。特に玄関や入口付近には門松やしめ飾りを配置し、新年を迎える神様をお迎えする意味を意識しましょう。正月飾りの種類や配置場所には地域差もありますが、一般的には入口・カウンター・個室の目立つ場所に飾ることで、お祝いの雰囲気を全体に行き渡らせることができます。
正月飾りを飾るタイミングにも注意が必要で、12月28日頃から30日までに設置するのが一般的です。29日は「苦」に通じるため避け、31日は「一夜飾り」と呼ばれ縁起が良くないとされています。実際に居酒屋で失敗しないためには、地域の慣習やお客様の層に合わせて、飾りのデザインや配置にも配慮が求められます。初めて飾る方は、正月飾りの由来やマナーについてスタッフ全員で共有し、統一感のある演出を目指しましょう。

鏡餅や門松など縁起物の意味と選び方
鏡餅や門松といった正月飾りには、それぞれ新年の幸福や繁栄を願う意味が込められています。鏡餅は円満や長寿、門松は神様を迎える目印としての役割があり、居酒屋においてもこれらの縁起物をバランスよく取り入れることが大切です。選ぶ際には、店舗の規模や内装に合ったサイズやデザインを意識し、和の雰囲気を損なわないようにしましょう。
また、しめ飾りや南天などの植物も人気の縁起物で、それぞれ厄除けや無病息災の意味を持ちます。誤った選び方をすると、店内の雰囲気にそぐわなかったり、逆にお客様に不快感を与えることもあるため注意が必要です。たとえば、鏡餅はカウンターの中央やレジ横など目につきやすい場所に、門松は入口の両脇に設置するのが一般的な方法です。縁起物の意味を理解し、店舗の特性や客層に合わせた選び方を心がけることで、より一層新年の演出効果を高めることができます。

伝統的な正月飾りを居酒屋で楽しむコツ
伝統的な正月飾りを居酒屋で楽しむためには、装飾だけでなく演出全体のバランスを意識することがポイントです。例えば、紅白の水引や松竹梅のモチーフを使ったテーブル装飾や、お正月限定のPOPを設置することで、店内の統一感を演出できます。また、照明やBGMも和の雰囲気に合わせて調整すると、より一層正月らしい空間が生まれます。
飾り付けの際は、通路やトイレなど動線を妨げないように注意し、安全性にも配慮しましょう。実際に「飾りが邪魔でお客様がつまずいた」という声や、「目立つ場所に飾ったことでSNS映えした」という成功例もあります。初心者の場合は、飾り付けの前にスタッフ全員でレイアウトを確認し、シミュレーションを行うこともおすすめです。お客様に安心感と華やかさを届けるためにも、定期的な飾りの点検や清掃も忘れずに行いましょう。

居酒屋ならではの正月飾り演出事例
居酒屋ならではの正月飾り演出には、店舗独自の工夫が光ります。たとえば、地元の特産品を使ったオリジナル門松や、地酒の瓶を利用した鏡餅風のディスプレイなど、地域性や店の個性を活かした飾り付けが好評です。カウンターや個室ごとに小さな正月飾りを配置することで、お客様一人ひとりに新年の祝福を伝えることもできます。
さらに、お正月限定のメニューやドリンクと連動した装飾POPを設置することで、来店動機を高める工夫も効果的です。実際に「正月飾りに合わせて特別メニューを提供したところ、常連客から好評だった」という声や、「写真を撮ってSNSで紹介してもらえた」という成功体験も聞かれます。失敗を避けるには、派手すぎず、清潔感を保った飾り付けを心がけることが大切です。

お正月飾りで伝統文化を発信する工夫
居酒屋でお正月飾りを活用することで、日本の伝統文化を発信する絶好の機会となります。飾りの意味や由来をPOPやメニュー表に記載したり、スタッフからお客様へ簡単な説明を加えることで、食事をしながら文化体験も楽しめる空間を演出できます。特に外国人観光客や若い世代には、こうした情報提供が喜ばれる傾向にあります。
また、地域の子どもたちと一緒に飾り作りワークショップを開催したり、伝統的な飾りの写真をSNSで発信することで、店舗の魅力向上や地域貢献にもつながります。注意点としては、宗教的な配慮や、過度な演出によるお客様の違和感に気をつけることが必要です。伝統を大切にしつつ、現代のライフスタイルや多様なお客様に合わせた柔軟な工夫を取り入れることが、居酒屋ならではの文化発信のポイントです。
飾る場所が決め手の居酒屋正月ディスプレイ術

居酒屋で正月飾りを置く最適な場所
居酒屋で正月飾りを置く際、最適な場所を選ぶことは店舗全体の雰囲気づくりに直結します。特に入口や玄関付近は新年の神様を迎える意味もあり、門松やしめ飾りを設置することで来店されるお客様に縁起の良い印象を与えられます。また、店内の主要な導線やカウンター周辺も目を引く場所としておすすめです。
正月飾りを置く場所を選ぶ際は、通路を塞がないように配置することが大切です。例えば、動線上に大きな鏡餅や松竹梅を置くと、移動の妨げになりかねません。お客様やスタッフが安全に行き来できるよう、スペースに余裕がある場所を選びましょう。
さらに、各テーブルや個室にも小さなしめ縄や南天、水引をさりげなく飾ることで、店内全体に統一感と華やかさを演出できます。これにより、来店された方がどの席でも新年の雰囲気を感じられるようになります。

入口やカウンターに映える飾り方の工夫
入口やカウンターは、居酒屋の顔ともいえる場所です。ここに正月飾りを配置する場合、門松やしめ飾りを左右対称に置くことで、バランスの良い見た目になります。特に門松は高さを意識して選び、店の規模に合ったサイズを選定しましょう。
カウンターには、鏡餅や水引を使った小ぶりな飾りを取り入れるのがポイントです。お客様の目線に自然に入る位置に設置することで、正月らしい華やかさが加わります。装飾の色合いは紅白や金銀など縁起の良いものを選ぶと、より一層新年のお祝いムードが高まります。
飾りの配置時には、食事やドリンクの提供の邪魔にならないように注意が必要です。実際にスタッフが動いてみて、導線や作業スペースに支障がないかを事前に確認すると安心です。

正月飾りでトイレや店内全体を華やかに
正月飾りは入口やカウンターだけでなく、トイレや店内全体にも取り入れることで、居酒屋全体の雰囲気をグレードアップできます。特にトイレはお客様が意外と目にする機会が多いため、ちょっとしたしめ縄や南天などの縁起物を飾ると、細部まで気配りが行き届いた印象になります。
店内の壁や柱には、お正月らしいPOPや装飾をポイントごとに配置しましょう。店舗の雰囲気やインテリアに合わせて、統一感を意識することが大切です。例えば、紅白の水引や松竹梅のモチーフを使うことで、お祝いムードを演出できます。
ただし、過度な装飾は圧迫感やごちゃごちゃした印象を与えやすいため、バランスを考えて配置することがポイントです。お客様の動線や視界を妨げないように心がけましょう。

居酒屋の特徴を生かしたレイアウト方法
居酒屋ならではのレイアウトを活かすには、店舗の広さや席配置に応じて正月飾りをアレンジすることが重要です。例えば、個室が多い居酒屋では各部屋ごとに小さな鏡餅や飾りを用意し、全体の統一感を演出できます。オープンな空間の場合は、中央に大きめの門松やしめ飾りを設置すると存在感が増します。
また、カウンター席の多い店舗では、カウンター上部や背面の壁に装飾を施すことで、お客様との距離感を保ちつつ新年の雰囲気を伝えられます。装飾の素材にもこだわり、和紙や竹、松など自然素材を活用すると、より落ち着いた和の空間が生まれます。
レイアウトを考える際は、店舗の導線やサービス提供の流れを妨げないように注意してください。スタッフの声として「飾りが多すぎると動きづらい」という意見もあるため、実際の現場での動きをシミュレーションして調整するのが成功のコツです。

お正月飾り配置でお客様の目線を意識
正月飾りの配置では、お客様の目線を意識することが大きなポイントです。来店時にまず目に入る入口やカウンター、座席から見える壁面など、自然と視線が集まる場所に飾りを設置することで、お祝いムードを感じやすくなります。
テーブルや個室の中にはさりげなく小さな飾りを配置し、派手すぎず上品な印象を大切にしましょう。例えば、南天や水引を使ったワンポイント飾りは、食事の邪魔にならず、和の雰囲気を演出できます。お客様から「細やかな気配りを感じられた」との声も多く、リピーター獲得にもつながります。
目線の高さや座る位置によって見え方が変わるため、実際に座って確認することも忘れずに。お正月飾りが視界を遮ったり、圧迫感を与えないよう、配置のバランスと量を調整することが大切です。
正月飾りのマナーや避ける日、実践のコツ

居酒屋で守るべき正月飾りのマナー解説
居酒屋で正月飾りを飾る際には、伝統的なマナーを守ることが大切です。まず、正月飾りには門松、しめ飾り、鏡餅などがありますが、それぞれの意味を理解した上で選びましょう。例えば門松は年神様を迎える目印、しめ飾りは悪いものを寄せ付けない役割があります。
店舗の入口やカウンター周辺など、人目につく場所に設置することで、お客様に新年の華やかな雰囲気を伝えられます。また、飾り付けの際は店舗の雰囲気や客層に合わせて、過度に派手すぎないバランスを意識することも重要です。特に居酒屋の場合、装飾が料理や接客の妨げにならないよう配慮しましょう。
実際に、常連客や初めての方から「店内の正月飾りが落ち着いていて良かった」という声も多く聞かれます。新年の演出を通じて、居心地の良さや日本らしさを感じてもらうためにも、基本的なマナーを押さえた飾り付けを心がけましょう。

正月飾りを飾ってはいけない日の注意点
正月飾りには飾るべき日と避けるべき日があるため、スケジュール管理が重要です。基本的には12月28日までに飾るのが良いとされますが、29日は「二重苦」と読めるため縁起が悪いとされています。また、31日は「一夜飾り」となり、神様に失礼とされるため避けましょう。
店舗運営上、年末は忙しくなりがちですが、正しいタイミングで飾ることでお客様にも安心感を与えられます。特に28日は縁起が良いとされるため、前倒しで準備するのがおすすめです。
実際に、年末の準備が遅れて31日に慌てて飾った場合、お客様から「慌ただしい印象を受けた」と指摘されることもあります。こうした失敗を防ぐためにも、事前にスケジュールを立てて適切な日に飾り付けを行いましょう。

タブーを避けるお正月飾りの飾り方とは
正月飾りには守るべきタブーがいくつか存在します。例えば、門松やしめ飾りを逆さまに飾ったり、汚れた状態で使用するのは失礼にあたります。また、他の季節の装飾と混在させるのも避けた方がよいでしょう。
飾りの設置場所にも注意が必要です。トイレやゴミ箱付近など不浄とされる場所には飾らないことがマナーです。また、鏡餅やしめ飾りは人が踏み入れない清潔な場所に置きましょう。地域や宗教によっても細かな違いがあるため、店舗の所在地の風習を確認することも大切です。
過去には、しめ飾りをエアコンの吹き出し口近くに飾ってしまい、落下や汚れでクレームにつながった事例もあります。飾り付けの場所や状態に注意し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

居酒屋で実践したい正月飾りのコツ
居酒屋で正月飾りを効果的に活用するには、店舗の雰囲気や客層に合わせた工夫がポイントです。例えば、入口には門松を、カウンターやテーブル周りには小ぶりのしめ飾りや南天を配置すると、空間全体が明るくなります。
また、装飾はシンプルかつ統一感を持たせることで、料理やお酒の印象を損なわずに新年の雰囲気を演出できます。ポップやレイアウトの工夫で、店内のどこにいても正月気分を感じられるよう配慮しましょう。装飾が邪魔にならないよう、動線やスタッフの作業スペースにも注意が必要です。
実際に、正月飾りを店内全体にバランス良く配置したことで、「写真映えする」とSNSで話題になった事例もあります。少しの工夫で、お客様に喜ばれる店舗演出が可能です。

会社や店舗での鏡餅の適切な場所選び
鏡餅は正月飾りの中でも特に重要な縁起物で、会社や店舗では設置場所に配慮する必要があります。基本的には店舗の中央や神棚、レジカウンターの近くなど、人の集まる目立つ場所が適しています。
一方で、床に直接置くのは避け、清潔で高い位置に飾ることがマナーです。また、調理場やトイレ付近など衛生面で問題がある場所も控えましょう。鏡餅はお客様やスタッフ全員が見える場所に設置することで、新年の願いを共有できる効果も期待できます。
過去には、鏡餅を目立たない隅に置いたため「存在に気づかなかった」と言われた事例もあります。店舗の印象作りのためにも、鏡餅の場所選びには十分注意しましょう。
装飾の種類選びで居酒屋に縁起を呼び込む方法

居酒屋で人気の正月飾り種類と意味
居酒屋でよく見かける正月飾りには、門松やしめ飾り、鏡餅といった伝統的なものがあります。これらは新年を迎えるにあたり、神様をお迎えし、店舗やお客様に福を呼び込む縁起物として用いられています。例えば、門松は松竹梅などの植物で作られ、長寿や繁栄を象徴し、玄関先に飾ることで新年の神様を招き入れる役割を担います。
しめ飾りは悪いものを寄せ付けず、清めの意味を持つため、入口やカウンター周りに飾られることが多いです。鏡餅は円満や調和を願う意味が込められており、居酒屋のレジ横やテーブル上に小型のものを置くケースも見られます。こうした正月飾りは、居酒屋の雰囲気を新年らしく華やかにし、来店するお客様にも季節の移ろいを感じてもらうために重要な役割を果たします。
ただし、飾りの種類や配置には地域差や店舗ごとのこだわりも反映されるため、意味を正しく理解し、店舗の雰囲気や客層に合わせて選ぶことが大切です。たとえば、南天や紅白の水引を加えると、より縁起の良い印象を与えることができます。

縁起を高めるための装飾選びのポイント
居酒屋で正月飾りを選ぶ際は、縁起物としての意味や由来を意識することが大切です。まず、店内外で目立つ場所に門松やしめ飾りを配置することで、来店客に新年の特別感を感じてもらえます。また、鏡餅や水引などの小物も活用し、細部まで気を配ることで店舗全体の雰囲気が一段と華やかになります。
装飾選びでは、派手すぎず落ち着いた色合いや素材を選ぶと、食事やお酒の場としての居酒屋の魅力と調和します。松竹梅や南天など、季節を感じさせる植物を使うことで、縁起の良さと季節感を同時に演出できます。さらに、飾るタイミングも重要で、一般的には年末の28日までに飾り付けを終えるのがマナーとされています。
失敗を避けるためには、地域の風習や店舗の規模、客層を考慮し、適切な大きさや種類の飾りを選ぶことがポイントです。たとえば、カウンター席が中心の小規模店なら小ぶりな正月飾りを選ぶなど、空間とのバランスを意識しましょう。

飾り種類別で変わる居酒屋の新年演出
正月飾りの種類によって、居酒屋の新年の雰囲気や演出が大きく変わります。門松を玄関に置くと格式高い印象を与え、しめ飾りを入口や厨房に飾ることで清潔感と安心感を演出できます。鏡餅を目立つ場所に置くと、円満や健康を祈る気持ちが伝わりやすくなります。
たとえば、和風居酒屋であれば、松や竹を使った伝統的な飾りが店内の雰囲気と調和しやすいです。一方、洋風居酒屋やカジュアルな店舗では、紅白の水引やポップな正月飾りをアクセントとして使うと、明るく親しみやすい新年の演出が可能です。店舗のコンセプトやターゲット層に合わせて飾りの種類やデザインを工夫することが大切です。
また、飾りの設置場所や数にも注意が必要です。例えば、カウンターやテーブル席ごとに小さめの飾りを配置することで、どの席からも季節感を感じられます。演出の工夫一つで、リピーターや新規客の満足度向上にもつながります。

しめ飾りや水引の活用で店舗らしさを演出
しめ飾りや水引は、居酒屋の個性やこだわりを表現するうえで非常に有効なアイテムです。しめ飾りは入口や厨房付近に飾ることで、邪気を払うと同時に、清潔感と新年の厳かな雰囲気を演出できます。水引はテーブルやお箸袋、レジ周りにアクセントとして使うことで、細やかな気配りを感じさせることができます。
たとえば、紅白や金銀の水引を使ったアレンジは、華やかさと縁起の良さを両立できるため、特に宴会利用の多い店舗で人気です。しめ飾りも、南天や松竹梅などの素材を加えることで、より店舗オリジナルの演出が可能です。お客様から「細部までこだわりを感じる」といった声が聞かれることも多く、新年の集まりにふさわしい空間づくりにつながります。
ただし、過度な装飾やスペースに合わない大きさの飾りは、かえって店舗の雰囲気を損なうことがあるため、全体のバランスを見ながら配置することが大切です。装飾の意味や地域の風習も確認し、店舗らしさと伝統を両立させましょう。

正月飾りpopで縁起の良い雰囲気をつくる
居酒屋では、正月飾りを活用したPOP(ポップ)も効果的な演出手段です。POPはメニューやおすすめ情報とともに、門松やしめ飾り、水引などのモチーフを取り入れることで、視覚的にも新年らしい華やかさと縁起の良さを伝えることができます。特に、手書きや和紙を使ったPOPは温かみがあり、店舗独自の雰囲気づくりに役立ちます。
また、正月飾りPOPには新年の挨拶やお祝いのメッセージを添えることで、来店客へのおもてなしの気持ちを表現できます。例えば「新年明けましておめでとうございます」「本年もよろしくお願いいたします」といった言葉を添えることで、店舗の温かさや親しみやすさが伝わりやすくなります。
ただし、POPのデザインや配置が派手すぎると、落ち着いた雰囲気を求めるお客様には不快感を与える場合もあります。装飾のバランスや色使いに注意しながら、縁起の良い雰囲気を演出しましょう。失敗例として、スペースを圧迫するほどのPOPを設置し、動線を妨げてしまったケースもあるため、設置場所やサイズ選びも慎重に行うことが重要です。